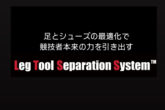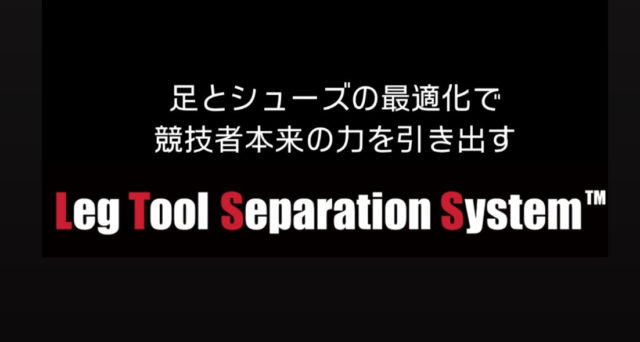サッカーストッキングだった時代からソックスの時代へ― LTSS設計思想とセパレートサッカーソックスの誕生 ―
2025.05.13
ストッキングだった時代からソックスの時代へ
サッカーソックスの設計思想「LEG TOOL SEPARATION SYSTEM(LTSS)」は、競技者本来の力を引き出すために、“足とシューズの最適化”を図る革新的なソリューションです。
私たちはこれを、単なるソックスの開発や、ソックスを分離して組み合わせるという発想にとどまらない、構造の再設計と位置づけています。
今回は、競技規則における「ソックスの呼称の変化」を入り口として、**サッカーソックスのセパレート化が“なぜ必要なのか”、そして“どのように有益なのか”**をお伝えしたいと思います。
― LTSS設計思想とセパレートサッカーソックスの誕生 ―
ソックスの呼称が変わった ― 2016年ルール改正
かつて、サッカー選手の足元を覆うものは「ストッキング」と呼ばれていました。
それは、**国際サッカー評議会(IFAB)**が定める「競技規則」でも同様で、第4条「競技者の用具」第2項に「Shin guards must be covered entirely by the stockings(すね当てはストッキングで完全に覆われていなければならない)」という文言が使われていました。
しかし、2016年のルール改正を境に、この“stockings”という表現が“socks(ソックス)”に変更されました。
この背景には、サッカーにおける用具の実態と役割の変化があります。かつては膝下全体を覆うハイソックス=ストッキングが前提でしたが、近年ではソックスやテープ、アンダーアイテムを組み合わせる選手が増加し、「一体型ストッキング」という概念が時代に合わなくなってきたのです。
ストッキングという呼称の意味と起源
「ストッキング(stocking)」とは、本来は脚を覆う筒状の衣料を指します。英語でも、膝下までの長い靴下やタイツの一種を意味し、見た目・形状から来た呼称です。
野球用語にも「ストッキング」という言葉が存在します。
特に日本では、「アンダーソックス」と「ストッキング(足掛け式)」が2層で構成され、高校野球連盟や全日本軟式野球連盟の規定で両方の着用が義務化されています。
メジャーリーグベースボール(MLB)でも、ストッキング(stirrups)は長らく伝統的なユニフォームの一部でしたが、1990年代以降、ズボンの裾を足首まで下ろすスタイルが主流となり、ストッキングは徐々に露出しなくなりました。それでも一部のチームや選手は、クラシックなスタイルを守り続けています。
サッカーにおける“ストッキング”の変遷
サッカーにおいては、ストッキングと呼ばれていた時代、シンガード(すね当て)を着けずにプレーする選手も多く、ハイソックスを足首まで下ろす姿も一般的でした。
それが大きく変わったのが1990年のルール改正です。
この年、IFABは「すね当て(shin guards)の着用を義務化」しました。
その背景には、ラフプレーによる負傷の増加や、スポーツとしての健全な発展を阻む危険性への懸念がありました。
実際、1990年の改正時の公式文書では、以下のように述べられています:
“The Laws of the Game must continue to evolve in order to protect the safety of players and to encourage skillful play over dangerous tactics.”
(競技規則は、選手の安全を守り、危険なプレーよりもスキル重視のプレーを促すために進化し続けなければならない。)
この変更により、ストッキングの“すねを覆う”役割が明確化され、統一された着用義務のある用具として定着していきました。
日本独自の文化 ― 足掛けストッキングの存在
欧州のトップレベルのフットボールシーンでは見かけることがほとんどなかったものの、日本では1980年代まで、サッカーにも“足掛けストッキング”という用具が存在していました。
これは、野球で使われる足掛け式ストッキングの影響を受けたもので、ショートソックスと組み合わせて着用するスタイルが、特にグラスルーツの現場で見られていました。
この足掛けストッキングこそ、LTSS設計思想のルーツのひとつです。
伝統と革新の接点にこそ、新しい解決策は生まれます。
そしてLTSSへ ― 分離の必然、再設計の思想
「サッカーソックスはこうあるべき」という固定観念を、構造的に問い直したのが**LTSS(Leg Tool Separation System)**です。
サッカーソックスを以下のように“分ける”ことで、部位や役割ごとの最適な設計を可能にします。
• 足部(フット部): セパレートソックス
• 脛部(レッグ部): セパレートストッキング
• 内部サポート機能: 着圧インナーストッキング

LTSSは、単なる「分離」ではない。
― 再定義と品質改良による“足とシューズの最適化” ―
LTSSは、単なる「ソックスを分けた構造」ではありません。
その本質は、競技者本来の力を引き出すための課題解決策の一つとして、足とシューズの関係を最適化することにあります。
現代のサッカーにおいて、パフォーマンスや怪我予防を左右するのは、シューズ単体ではなく、足・ソックス・シューズの一体的な機能設計です。
つまり、ソックスは単なる「中間にある布」ではなく、**足とシューズをつなぐ“インターフェース”**として再定義されるべきなのです。
そのためにLTSSが採ったアプローチは、役割と構造の両面での分離と最適化でした。
• 構造上の分離:
一体型ソックスを、足部の「セパレートソックス」と脛部の「セパレートストッキング」に分離。
• 機能上の分離(同一部位内):
ストッキングの内側に、段階着圧の「インナーストッキング」を追加。
見た目の役割(チームカラー・統一性)と、パフォーマンス補助(着圧・疲労軽減)を別構造で対応。
これにより、求められる機能ごとに最適な素材・設計を選択できる自由度が生まれます。
一見すると「ただ分けただけ」に見えるかもしれませんが、実際には足部の構造、運動生理学、競技特性、用具の特性など、複数の視点から再構成された設計思想なのです。
選手とチームに伝えたいこと
いま、サッカーソックスは選べる時代へと進んでいます。
かつての一体型ストッキングから、構造と機能を分けた新しい選択肢へ。
• 選手には、「自分に合ったソックス選び」を。
• チームエキップメント担当者には、「選手のための最適なストッキング選び」を。
その一歩が、パフォーマンスの違いに、そして怪我予防や快適性の違いに、確実につながっていきます。
革新と歴史のあいだで
― KAKU SPORTS OFFICEの取り組み ―
私たちKAKU SPORTS OFFICEの使命は、サッカーという競技を構成する用具を、構造から再定義しなおすことです。
革新は、歴史や伝統を再発見し、継承することから生まれる。
そのひとつの形が、**LTSS(Leg Tool Separation System)**であり、
その設計思想の中には、足掛けストッキングという日本独自の用具文化の記憶も息づいています。
お問い合わせ
KAKU SPORTS OFFICE
ご質問・ご相談はこちらまで:contact@kakusportsoffice.com
フットボールクリエイター 角田壮監
足とシューズの最適化で競技者本来の力を引き出すという視点から世界初のサッカーソックスの構造を分離させ、完成されたセパレートサッカーソックスLeg Tool Separation Systemを考案。
「競技者本来の力を引き出す」ためにを理念に、グローバルシーンで実績を残している様々な競技のトップアスリートや競技団体のマネジメントやディレクションで培った「競技力向上のための組織づくり」をはじめ、社会にスポーツが持つ有益な効果を生み出すためにスポーツシステムコーディネーター、スポーツプロデューサー、プロジェクトコンサルタントとして、次世代ニーズを見据えた魅力ある競技スポーツシーンの創出に努めている。
KAKU SPORTS OFFICE MISSION
アスリート思考で心豊かな社会づくりをクリエイトする
KAKU SPORTS OFFICEは、「アスリート思考で心豊かな社会を創造する」をモットーに、競技スポーツに関わる個人・企業・団体の活動や事業を、的確な視点で分析します。そして、言語・文化・音楽・映像・活字といった多様な“シンボル”を活用し、人と人、組織と組織、企業と企業、人と組織・企業といったあらゆるつながりの中から、最大の相乗効果を生み出す組み合わせをコーディネート。新たな利益システムを構築するコミュニケーションコーディネーターとして活動しています。
また、創業者・企画者としての精神をもとに、理念や目的を共有できるパートナーの育成や、持続的かつ自走可能な組織づくりを支援するシステムコーディネーターとしても貢献。さらに、競技者一人ひとりが本来持つ力を引き出すメンターとして、競技スポーツの発展にも寄与しています。